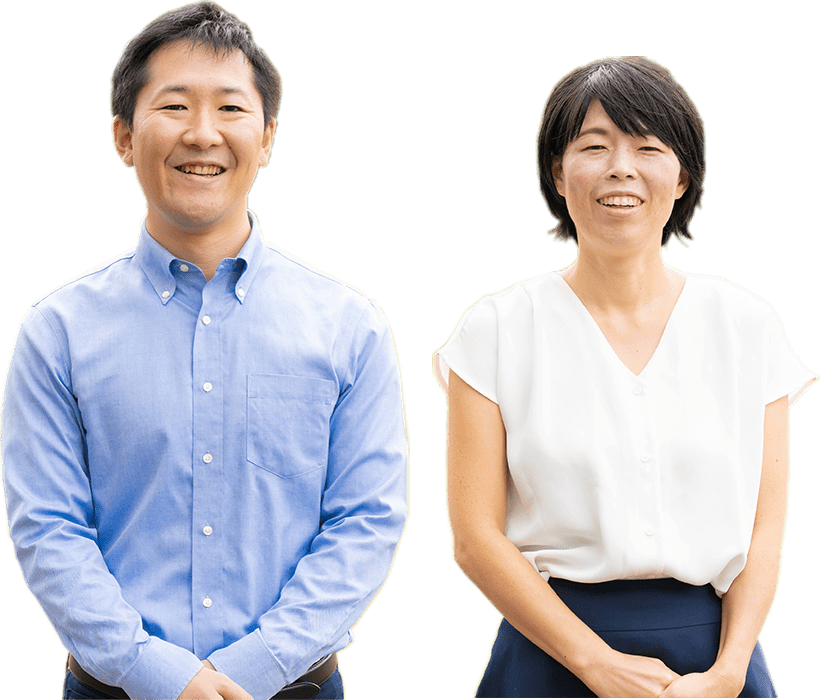【サイバー攻撃を受けるとどうなる?】被害例や多発しているサイバー攻撃を解説
- Webサイト保守
- WordPress
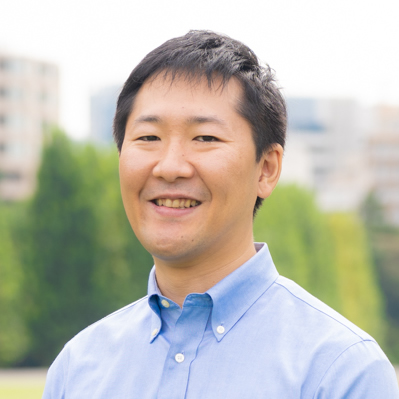
記事の監修
IT・WEB集客の専門家
波多野 明仁(Akihito Hatano)
WEB業界歴22年。学生時代に50サイトの制作・運営を行い収益化を達成。その後、ITシステム開発会社にてSEを6年間経験し独立。東証プライム企業をはじめ4,000サイト以上を改善してきた実績あり。自社メディアの制作・運営で培ったアクセスアップのノウハウをクライアント企業のWEB集客に活かし、日々活躍中。1年でアクセス数が715倍に増加した企業や、売上が25倍に増加した企業など、法人クライアントの実績多数。

こんにちは、株式会社ソライル Web集客コンサルタントの波多野です。
「サイバー攻撃は怖いもの」ということは把握していても、被害に遭ったときに具体的にどのような状況になるのか疑問に感じていませんか。
今回は、サイバー攻撃を受けるとどうなるか、サイバー攻撃の種類別の想定される被害、国内で多く見られるサイバー攻撃と被害内容について解説します。
さらに、サイバー攻撃に効果的な対策もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
サイバー攻撃とは

サイバー攻撃とは、ネットワークを通じてサーバーやパソコンといった情報端末に対し、データの窃取や改ざん、営業妨害などを試みる悪意ある行為です。
攻撃者は、悪意を持った個人・サイバー犯罪組織・産業スパイ・ハクティビストなど様々で、それぞれ金銭盗取や情報窃取、企業のイメージダウン、政治的・社会的主張といった目的に応じて攻撃を行います。
高度化・巧妙化した攻撃が世界中で発生している今、ターゲットにされる可能性は決して珍しくないため、適切な対策が必要です。
サイバー攻撃を受けるとどうなる?

サイバー攻撃を受けると、下記5つのような被害が起こり得ます。
- ・情報漏えい
- ・システム停止・機能停止
- ・金銭的損失
- ・信頼の失墜
- ・加害者となることもある
上記5つの被害について解説していきましょう。
情報漏えい
サイバー攻撃によって、個人情報や会社の情報漏えいが考えられます。
名前や住所、クレジットカードや銀行口座など、特定の個人を特定できるような情報や、企業が機密にしている有用な技術や営業上の情報が盗まれる被害は、後を絶ちません。
情報が流出した場合、アカウントの乗っ取りや金銭の窃取、非合法の情報が集まるWebサイト「ダークウェブ」での売買などで使われる可能性があります。
さらに、情報を守れなかったことで罰金や懲役刑に科せられることもあるうえ、損害賠償請求や社会的信用の失墜も起こり得るでしょう。
システム停止・機能停止
サイバー攻撃を受けることで、システム停止・機能停止が発生することもあります。
例えば、「DoS攻撃・DDoS攻撃」と呼ばれる、特定のWebサイトやサーバーに悪意を持って大量のデータを送りつけるサイバー攻撃によって、ネットワークが遅延したりシステムが停止したりすることも。
また、不正アクセスを確認した場合、これ以上被害を拡大させないためにシステムや機能を停止させる場合もあります。
その結果、売上減少はもちろん、サービスを利用できなかった取引先・ユーザーの不満によって、企業のブランドイメージが損なわれてしまうことも考えられるでしょう。
金銭的損失
サイバー攻撃のターゲットになると、下記のような金銭的損失も発生します。
| コストの種類 | 概要 |
| 直接コスト |
|
| 復旧コスト |
|
| 再発防止コスト |
|
このように、サイバー攻撃で直接発生する費用だけではなく、復旧や再発にも様々なコストがかかるため、損益が数億円に達するケースも珍しくありません。
信頼の失墜
サイバー攻撃を受けた企業は、「セキュリティに脆弱性があった」と考えられ、顧客や取引先、投資家から大きな信頼を損なう可能性があります。
製品やサービスの利用を避けられたり、取引停止や新たな取引の機会を失ったり、さらに株価が下落したりすることで、金銭的被害は大きくなるでしょう。
また、一度失墜した信頼を取り戻すことは困難であり、時間もかかります。
中には、サイバー攻撃によって企業ブランドの価値が損なわれてしまい、事業を続けることが難しくなる場合もあります。
加害者となることもある
サイバー攻撃によって、被害者だけではなく「加害者」になることも考えられます。
例えば、自社のWebサイトに悪意のあるコードが仕込まれ、サイトを閲覧したユーザーのパソコンにウイルスが感染した場合、自社は「加害者」として対応しなければいけません。
また、最近はセキュリティ対策の甘い中小企業のネットワークから、取引先企業のネットワークに侵入し、情報や金銭窃取、不正プログラムの設置などを行うケースも続出しています。
【代表的なサイバー攻撃の種類】想定される被害とは?

こちらからは、代表的なサイバー攻撃の種類別に想定される被害をご紹介します。
- ・マルウェア
- ・ランサムウェア
- ・DoS攻撃・DDoS攻撃
- ・サプライチェーン攻撃
- ・フィッシング
- ・ゼロデイ攻撃
- ・標的型攻撃
サイバー攻撃対策を行ううえで、参考にしてみてください。
マルウェア
マルウェアとは、悪意のあるプログラムやソフトウェアを総称する言葉であり、「悪意のある(malicious)」と「ソフトウェア(software)」を組み合わせた造語です。
コンピューターウイルスや、無害なプログラムを装って端末内部に侵入し悪事を働く「トロイの木馬」などが挙げられ、メールの添付ファイルや不正なソフトウェアのインストール、ソフトウェアの脆弱性を突いた侵入などにより感染します。
マルウェアに感染すると、情報の窃取やファイルの改ざん、さらにデバイスやWebサイトを乗っ取られて攻撃の踏み台にされるなどの被害が考えられます。
ランサムウェア
ランサムウェアとは、データを暗号化して使用不可能な状態にし、復元と引き換えに身代金を要求するサイバー攻撃です。
ランサムウェアで暗号化されたデータを自力で復元することは困難であり、身代金を支払っても元に戻るとは限りません。
感染経路としては、電子メールやネットワーク機器の脆弱性を狙った侵入などが挙げられ、感染することでシステム障害が発生し業務停止に陥る可能性があります。
最近は、データを窃取したうえで「身代金を支払わなければデータを公開する」といった手口が流行しています。
DoS攻撃・DDoS攻撃
DoS攻撃やDDoS攻撃とは、攻撃者がWebサイトやサーバーに対して大量の情報を送り、機能停止に追い込むサイバー攻撃です。
DoS攻撃は、1台のコンピューターから大量のデータを送りつける攻撃であり、遮断も比較的容易なものでした。
しかし、最近ではDDoS攻撃と呼ばれる、複数のコンピュータから同時に大量のデータを送る手口が主流であり、サービスを停止させて売上損失や信用失墜といった被害をもたらしています。
また、DDoS攻撃を事前に予告し、停止する代わりに身代金を要求したり、政治的・社会的な抗議手段として実行されたりするケースも増加しています。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃とは、セキュリティ対策に弱点のある企業をターゲットとし、脆弱性を悪用しながらその企業の取引先やソフトウェアなども攻撃する手口です。
標的組織に直接攻撃をするのではなく、関連会社や取引先などの脆弱性をついて攻撃を仕掛け、その企業を踏み台に不正アクセスや情報窃取などを行います。
一方で、ソフトウェア開発企業のシステムに侵入して、正規のソフトウェアそのものに不正なコードを混入させたり、サービス事業者を侵害して該当のサービスから顧客に攻撃を仕掛けたりする事例も発生しています。
被害としては、個人情報や機密情報の窃取、不正アクセスによる業務停止などが挙げられるうえ、「加害者」として損害賠償の請求などが求められる場合もあるのです。
フィッシング
フィッシングとは、情報を摂取することを目的に仕掛けられるサイバー攻撃です。
正当な差出人を装った偽のメールを送ったり、公式サイトを装った偽のWebサイトから個人情報を入力させて騙し取ったりする方法があります。
自社になりすましたフィッシングサイトが発生すると、顧客からの信頼が失墜したり、企業ブランドのイメージに傷がついたりするため、売上低下を招く恐れがあります。
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃とは、ソフトウェアの脆弱性を修正するためのプログラムが提供される前に、その脆弱性を悪用して攻撃を仕掛ける手口です。
根本的な対策が難しいサイバー攻撃であり、未知の脆弱性を突いた攻撃の場合は攻撃されていることに気づくことも困難といえます。
ゼロデイ攻撃を受けることで、情報漏えいやマルウェア感染、システムダウンやランサムウェア攻撃、社会的信用の低下や取引停止などの被害が考えられるでしょう。
標的型攻撃
標的型攻撃とは、特定の組織や業界、地域などをターゲットに攻撃を仕掛ける手口です。
ターゲットに取引先などを装ってメールを送り、ターゲットが添付ファイルを開くとマルウェアに感染するといった手法や、Webサイトの改ざんなどが挙げられます。
Webサイトの改ざんの場合、意図に反する不適切な情報発信や、ユーザーへのマルウェア感染などが起こり得ます。
このような標的型攻撃により、情報漏洩や金銭的被害、社会的信用の低下や業務停止、さらに「加害者」となる可能性も考えられるでしょう。
国内で多く見られるサイバー攻撃と被害内容

警察庁サイバー警察局の資料によると、令和6年においてDDoS攻撃とみられる被害や情報窃取を目的としたサイバー攻撃、さらにランサムウェアの被害が相次いで発生しました。
令和6年6月には、出版大手企業のサーバーがランサムウェアを含む大規模な攻撃を受け、25万人分を超える個人情報や企業情報の漏えいと、20億円を超える損失が見込まれています。(参照:2024年3月 警察庁サイバー警察局 令和6年における サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について)
サイバー攻撃の被害事例

日本では、大手損害保険会社において75,000件の個人情報が閲覧された可能性や、大手通信事業者に大量のデータが送られてサービスがつながりにくくなる不具合が発生しています。
最近では、複数の関与者が役割を分担してサイバー攻撃を仕掛けることで、専門知識がなくても攻撃を仕掛けられる状況になっているため、より強固な対策が必要といえるでしょう。
サイバー攻撃に効果的な対策

こちらからは、サイバー攻撃に効果的な対策を「個人向け」と「会社向け」にわけてご紹介します。
個人で行う対策
個人が行うべき有効な対策としては、以下の通りです。
- ・システムを常に最新に保つ
- ・長く複雑なパスワードを設定する
- ・不審なメールやWebサイトを警戒する
- ・不要なアカウントを削除する
- ・ウィルス検知ソフトを導入する
OSなどのシステムは随時脆弱性を修正するソフトが公開されているので、アップデートを忘れないようにしましょう。
会社で行う対策
会社では、個人で行うべき対策に加えて、以下のような対策を行ってみましょう。
- ・セキュリティポリシーを策定する
- ・セキュリティソフトを導入する
- ・ネットワークの共有範囲を適切に設定する
- ・定期的にデータのバックアップを行う
- ・インシデント対応計画を策定する
特に、企業の情報を守るセキュリティシステムの導入は、必ず実施するべき対策の1つです。
セキュリティシステムは、ファイアウォールや侵入検知システム(IDS)など様々な種類があるため、自社に適したものを選び導入することが大切といえます。
サイバー攻撃に不安を感じたら専門家に相談しよう

現在、サイバー攻撃に不安を感じている方は専門家に相談することがおすすめです。
高度な専門知識や経験に基づき、現状のリスクを把握したうえで、適切なサイバー攻撃の対策を実施してもらえます。
サイバー攻撃による、情報漏えいやシステム停止・機能停止などの被害を未然に防げるうえ、万が一インシデントが発生した際も迅速な初動対応により被害の拡大を防げるでしょう。
ソライルでは、「サイバー攻撃された7つのサイト全てを半日で復旧」「復旧専門業者で直せなかったサイトを作業開始当日に復旧」といった数々の実績を持つプロが、確かな技術で貴社サイトをお守りします。
甚大な被害を受けてしまう前に、お気軽にご相談ください。
→ソライルのWebサイトのサイバー攻撃復旧サービスの詳細はこちら
サイバー攻撃を受けるとどうなる?まとめ

今回は、サイバー攻撃を受けるとどうなるか、サイバー攻撃の種類別の想定される被害、国内で多く見られるサイバー攻撃と被害内容について解説しました。
サイバー攻撃を受けると、個人情報や機密情報の漏えい・システム停止・莫大な金銭的被害・企業の信用失墜・加害者となるリスクが考えられます。
Web業界歴20年以上のソライルでは、ITの国家資格を持ったプロがSEO対策にも効果のあるWebサイトの保守・運用管理を担当いたします。
関連記事